
有事に企業を止めない─BCPとレジリエンス再構築の時代へ (第3回:「レジリエンスとエネルギー戦略の重要性」)
「止まらない会社」はどうつくるのか。
いま、企業には “生き抜く力” が問われています。
地震・風水害・パンデミック・サイバー攻撃・サプライチェーン寸断──
有事は複雑化し、そして「連鎖する時代」に入りました。
かつての 「BCP=災害対策マニュアル」 では、もう立ち行かない。
AI・DX時代、エネルギー自立・分散化の時代にふさわしい、
「動き続けられる企業」「再起動できる企業」 への進化が必要です。
本シリーズでは、社会文化研究家・池永寛明氏へのインタビューを通じて、「未来志向型BCP再設計」の視座と実践ステップ を、全6章にわたって解説します。
これからの企業経営に不可欠な、“未来戦略としてのBCP” のあり方をともに考えていきます。
目次
プロフィール

池永寛明(いけながひろあき)
社会文化研究家(元 大阪ガスエネルギー・文化研究所所長、元 日本ガス協会企画部長)
(略歴)大阪ガス株式会社理事・エネルギー・文化研究所長・近畿圏部長・日本ガス協会企画部長
(現在)日本経済新聞note 日経COMEMO キーオピニオンリーダー(https://note.com/hiroaki_1959)
関西国際大学客員教授・データビリティコンソーシアム事務局長・Well-Being部会会長・
堺屋太一研究室主席研究員・未来展望研究所長・IKENAGA LAB代表等
(著書) 「日本再起動」「上方生活文化堂」など
第5章|「1週間自給」のエネルギー構想──“止まらない設計”が企業を救う
エネルギーを“動脈”ととらえた、多層的エネルギーBCP戦略。
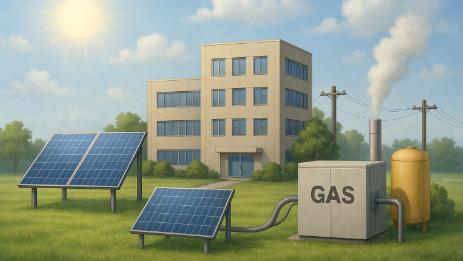
「BCPで大切なのは最初の72時間」──
そう語られたのは、2011年の東日本大震災の教訓にもとづいたものでした。
しかし、2025年の今、それはもはや過去の常識です。
当時は「3日間を乗り切れば、電力・ガス・水道・交通・サプライチェーンも徐々に復旧する」前提がありました。
ところが現在では
・気候変動
・AI化
・都市集中型インフラ
・グローバル物流依存
・人手不足と高齢化
こうした要因により、「想定以上の復旧遅延」 が現実的なリスクとなっています。
もはや “3日しのぎ” では不十分。
本気で「止まらない会社」をめざすなら、「1週間自給できるエネルギー構想」 が不可欠です。
電力が止まると「すべてが止まる」
忘れてはならないのは、エネルギーが止まれば業務も人命も守れないという現実です。
・空調・情報システム・冷蔵・冷凍庫 → 食品や薬品の保存不能
・エレベーター・給排水 → 高層ビルでは人の移動困難
・IT機器・通信設備 → 情報が届かず判断も行動もできない
・自家発電機があっても燃料(軽油・LPガス)が届かない
つまり、エネルギーこそBCPの“基盤”であり“動脈”です。
ここが確保できなければ、いかに高度なBCPやマニュアルも機能しません。
「自前で1週間をしのぐ」ための具体シナリオ
では、1週間の自立的エネルギー運用はどう設計すべきか?
求められるのは多層的・分散型のエネルギー戦略です。
① 太陽光発電+蓄電池による昼夜の電源確保
・太陽光パネル → 日中発電
・蓄電池 → 夜間使用
・電気自動車(EV) → 移動電源車として活用
・IT・照明・通信など基幹業務用負荷をカバー
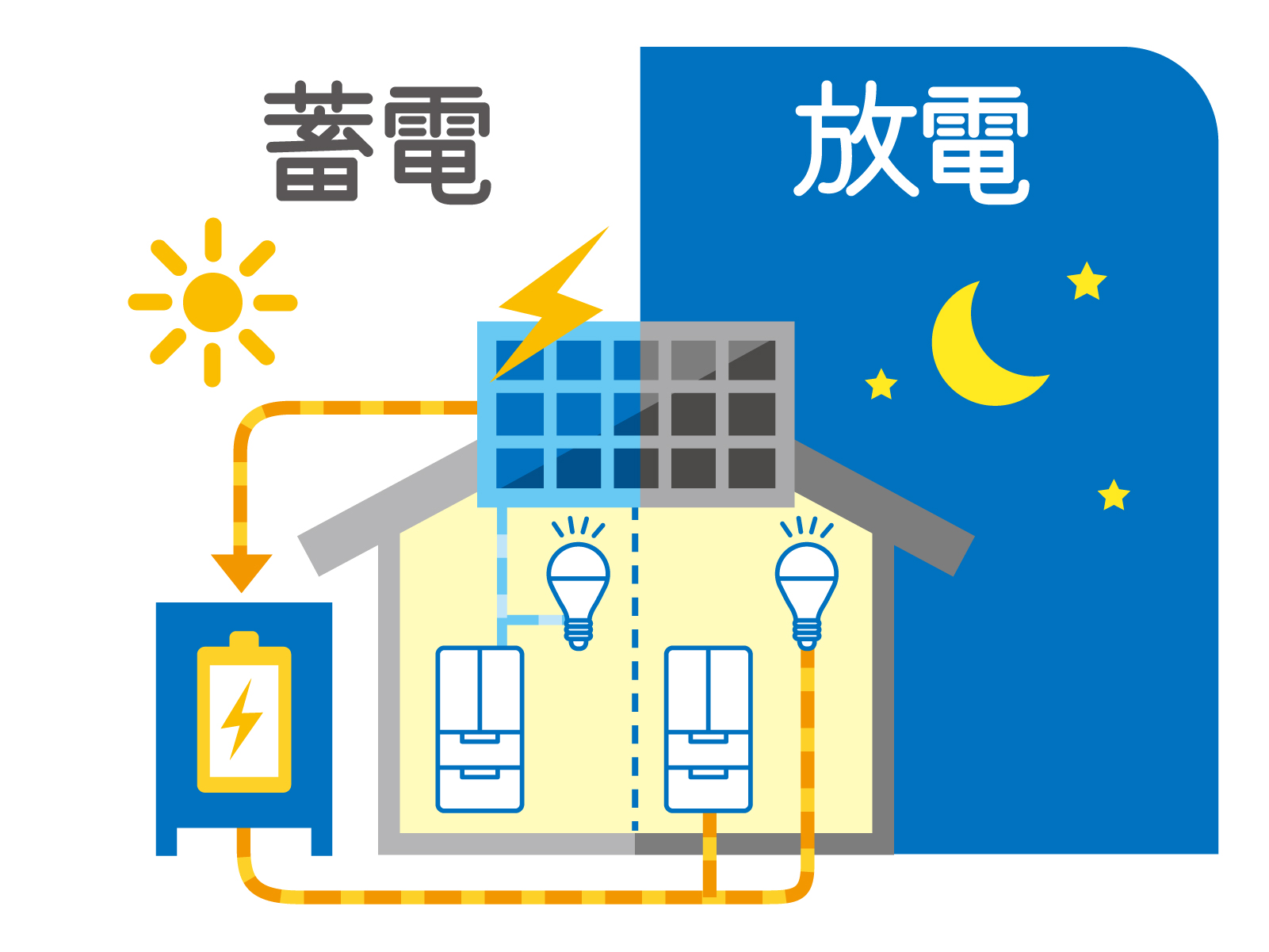
② BOS型ガスコージェネレーション
・都市ガス・LPガス → 発電+熱供給
・病院オペ室・冷凍庫・避難所通信・照明など命に直結する設備に対応
・起動信頼性が高く、エネルギーセキュリティを確立

画像出典:大阪ガス株式会社「コージェネレーションのバリエーション」
③ 非常用燃料の備蓄と更新体制
・軽油・ガスボンベ → 回転備蓄(期限前に使用・補充)
・使用量試算 → 年間補充計画
・「あっても使えない」 事態を防ぐチェック体制

④ 周辺地域・取引先とのエネルギー相互支援ネットワーク
・地元の工場・病院・物流倉庫等と「エネルギー融通協定」を締結
・災害時、発電設備の開放や物資の融通
・行政との 「災害時施設提供協定」 も組み合わせる

「経済性」や「環境性」だけでは足りない時代へ
これまでエネルギー選択・投資の評価軸は:
・経済性(コスト)
・環境性(CO₂削減)
の2軸が主流でした。
これからは、「レジリエンス性」 という第3の軸が不可欠です。
チェックポイント例
・単一エネルギー源に頼っていないか(冗長性)
・電力の流れが 「可視化」 されているか
・停電時に 「なにを残し、なにを捨てるか」「何が止まり、何が動くのか」 を選択できる設計か
「レジリエンス性」 は
「投資回収年数」 や 「カーボンニュートラル目標」 と並ぶ、新しい経営判断の重要な物差しになる時代です。
エネルギーBCPは地域共助のインフラになる
企業がエネルギー自給・自立構想を持つことは、自社BCPの範囲を超える価値を生みます。
例
・自家発電設備を持つ工場・施設が近隣住民の一時避難所となる
・余剰電力で医療用薬品・ワクチンの地域保管を行う
・太陽光+蓄電システムを地域で共有活用
・EVへの充電 → 他重要施設へ移動電源車として提供
こうして「助けてもらう側」から「支える側」へ。
この発想こそが、新たな企業価値を創出するのです。
終章|レジリエンスは“未来戦略”である

企業が生き残るために必要なのは、リスクを恐れることではありません。
「何が起きても動ける」構えと仕組みを持つことです。
BCPは、もはや災害対応だけのものではありません。
・地政学リスク
・パンデミック
・サイバー攻撃
・少子高齢化
・人手不足
・食料危機
・社会構造変化
現在、これからの有事は「連鎖する」 時代です。
だからこそ、BCP=企業の未来戦略と位置づけるべき時代が始まっています。
経営の中心に据えて再構築するテーマ
・有事想定
・エネルギー戦略
・人材育成
・業務構造
・AI設計
・企業文化の“中核”
これこそが、「止まらない会社」から「再起動できる会社」 への進化であり、未来を生き抜く企業の新たな基盤となるのです。
以上。
























